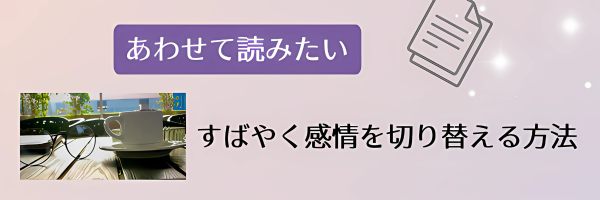数年前、私は仕事のことで悩んでいました。決断を前にして、ギリギリのところで迷い、踏ん張っている状態でした。
不思議なもので、人生にはときどき、救いのような時間があります。
その頃、本はほとんどネットで買っていたのですが、その日はなぜか、ふらりと本屋に立ち寄りました。
大好きなお菓子の本を探して棚を移動しているうちに、それほど分厚くない一冊を、手に取っていたのです。
偶然出会った一冊の本
それが、『ネガティブ・ケイパビリティ ――答えの出ない事態に耐える力』(帚木蓬生 著)でした。
「答えの出ない事態に耐える力」。
ネガティブ・ケイパビリティという言葉を、私はこのとき初めて知りました。
この一冊に出会うまで、無意識のうちに、同じ思考を何度もループさせていたことに気づかされたのです。
「早く答えを出したい」という癖
私は、身のまわりに余計なものを置かず、常にすっきり整えておきたいタイプ。
だから、気になることがあると、つい思うんです。
「早く答えを出したい」
「はっきりさせたい」
人は日々、決断の連続の中で生きています。解決を急ぐ瞬間は、日常のなかに常にあるわけです。
けれど、もし「答えを急がないこと」ができたら、少し無敵になれるかもしれない。
そんな思いで、ページをめくりました。
不安なとき、人は左脳モードになる
人は、先の見えない状況に置かれると不安を感じ、そこから抜け出すために「解決」を急ぎます。
このとき、判断や分析を優先する「左脳モード」の状態に傾きやすくなります。
焦りが、心と身体に負荷をかける感覚。
誰もが経験しているのではないでしょうか。
本の中には、こんな言葉がありました。
「不安や迷いは、すぐに解決できなくてもいい」「曖昧な状態に身を置くことで、新しい気づきが生まれる」
曖昧な状態の中。そんな場所で、どうすればいいのでしょうか。
曖昧さのなかで得られるもの
曖昧さとは、右でも左でもない場所に立つこと。正しいか、間違っているか、という二極から離れた中庸の位置です。
ジャッジのない視点を持つことで、人や物事を360度の視野でとらえることができます。
たとえば、時間に遅れて言い訳をする人がいたとします。
立ち位置を変えれば、それは「言い訳」ではなく「説明」とも受け取れるわけです。
心理学の研究でも、「結論を急がない人ほど、長期的に柔軟な思考を保てる」と言われています。
スタンフォード大学の研究でも興味深い報告があります。
「すぐに答えを出す」よりも「立ち止まる時間を持った」グループの方が、より創造的な解決策を導き出したそうです。
日常でできること

これは特別な才能ではなく、誰もが日常に取り入れられる身近な力です。
私が今、続けているのは「自分を俯瞰する」瞑想です。
目を閉じ、現実の視覚情報を遮断します。雑念が浮かんでも気にせず、ただ目を閉じたままで。
ある瞬間から、瞑想している自分を俯瞰で、遠くから眺めているような位置へ意識を移動させます。
夢の中で「これは夢だ」と気づく、明晰夢のように、「これはすべて夢だ」と感じてみてください。
心がぼんやりとして、落ち着いてきます。
自分の思考や感情を一歩引いて眺めてみる。それだけで、抱えている問題との距離感がふっと変わってくるのです。
身体の内側からバランスを整える
心の持ち方だけでなく、身体からのアプローチも私を助けてくれる大切な手段です。
長年、アーユルヴェーダを通じて心身の調和を探求してきました。
アーユルヴェーダの視点では、答えを急ぎすぎるときは、ヴァータ(動きと変化のエネルギー)が高まっている状態。
つまり、内側のエネルギーが少し浮き足立っている状態といえます。
このバランスが崩れた時、温かく、しっとりした甘みのあるもので、自分を優しくグラウンディングさせてあげます。

・煮りんご
・甘酒
・ホットミルク(私はオーツミルクを使います)にシナモンとターメリック
ドライフルーツのような乾燥した食べ物は控え、内側を潤してあげること。
体の内側からバランスを整えることは、乱れた心をそっと落ち着かせるための、私なりの「調律」です。
最後に
人生には、すぐに答えが出ない問いがあります。
しかし、その問いと一緒に立ち止まる時間が、私たちの視野を広げてくれるのです。
フルーツも、まだ青いうちに切ってしまうより、ただ曖昧な状態で置かれている時間の中で、少しずつ熟していきます。
答えを出せない時間も、きっと同じ。行き先の決まらない場所で、私たちは静かに甘さを深めている。
曖昧さの中に身を置くこと。それは、ひとつの成熟なのかもしれません。